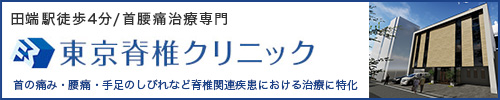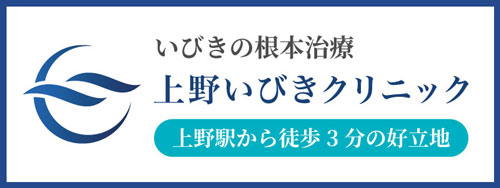頚椎手術とは?術式の違いと選択のポイントを徹底解説

院長監修記事
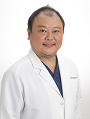
梅林 猛
東京脊椎クリニック院長/日本脳神経外科学会専門医/日本脊髄学会指導医
医療法人メディカルフロ ンティアでは脊椎手術に特化した医療施設(東京脊椎クリニック)を運営しています。
その施設の責任者である梅林猛医師監修の下、脊椎疾患や手術術式についても寄稿していきます。
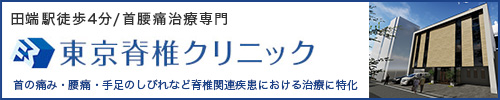
パソコン作業やスマホ操作が日常化した現代社会において、長時間の前傾姿勢が原因となる頚椎の障害が増えています。肩こりや首の痛みにとどまらず、手指のしびれや脱力といった症状が現れた場合、頚椎の手術が検討されるケースもあります。
東京脊椎クリニックでは手術担当医師全員が脳神経外科専門医であり、脳へかなり近い頚椎手術を得意としており手術症例数が非常に多い傾向にあります。頚椎手術はその部位からも構造が非常に複雑で頚椎(首の骨)が密集している部位でもあり、高度な技術と経験および専用の医療機器が必要のため対応できる医療機関が非常に少ないのが現状です。
本記事では、東京脊椎クリニックで実際に行っている頚椎手術の適応から主な術式、それぞれのメリット・デメリット、術後のリハビリまでを解説します。
1. 手術の適応とは?
多くの頚椎疾患は保存療法(薬、注射、リハビリ)で改善しますが、以下のようなケースでは手術が考慮されます。
- 6週間以上の保存療法でも改善が見られない
- 筋力低下や歩行障害など、神経の明らかな障害がある
- MRIやCTで神経の強い圧迫が認められる
- 頚椎の不安定性や骨棘による圧迫
2. 主な術式とその特徴
①椎弓形成術(ラミノプラスティ)
当院で最も多い手術でその適応も全国的に非常に多い手術ですが、施行できる医療機関がまだまだ少ないのが現状です
ラミノプラスティ(laminoplasty)は、頚椎後方から脊髄を減圧する手術で、「椎弓形成術」と訳されます。
1970年代に日本で開発された術式で、椎弓(背骨のアーチ部分)を“開いて”スペースを確保するのが最大の特徴です。切除ではなく、「温存・再配置」による減圧という点で、従来の椎弓切除術と区別されます。
🔵 メリット:広範囲な圧迫解除が可能
1. 複数の椎間にわたる狭窄(多椎間)に対応可能
-
頚椎症性脊髄症や後縦靭帯骨化症(OPLL)などの C2~C7といった広範囲にわたる狭窄 に対し、前方法(ACDF)では複数回の手術や融合が必要になりますが、ラミノプラスティは 後方から一度に広く減圧 できる利点があります。
2. 脊髄の移動を促すスペース確保

-
「ドアを開けるように」椎弓の片側を切開し、もう一方を蝶番(ヒンジ)として残すことで、 椎弓全体を外側に開き、脊髄の後方移動(ドリフト)を促します。
-
結果として、脊髄前方の骨化や椎間板の突出による圧迫から逃がすことができます。
3. 椎体の安定性を温存できる
-
椎弓を完全に切除するのではなく再構成するため、脊椎の支持構造を保ちつつ減圧が可能です。これにより、術後の不安定性や変形を起こしにくくなります。
4. 術後の再狭窄リスクが低い
-
単なる椎弓切除(ラミネクトミー)に比べて、椎弓形成術では再度骨が戻ってくる(骨再生)リスクが低く、持続的な除圧が期待できます。
🔴 デメリット:術後の肩こりや筋緊張の持続
1. 後頚部筋の侵襲
-
椎弓形成術では後方から筋肉を剥離するため、後頭下筋群や僧帽筋上部などを一時的に傷つけることが不可避です。
-
この侵襲により、術後に「首の重さ」「肩のだるさ」「突っ張り感」といった 慢性的な筋緊張症状(axial pain) を訴える患者が一定数存在します。
2. 首の可動域の減少
-
椎弓を広げて固定することで、頚椎の後屈(反らす動き)を中心に可動域が10〜20%程度減少することがあります。
-
可動域制限は直接的な痛みではありませんが、筋肉の硬さや動かしにくさとして不快感に繋がることがあります。
3. Axial pain(軸性疼痛)
-
欧米の文献でも「Axial neck pain」は後方アプローチ後の主要合併症として認識されており、術後1〜2年経っても継続する例が約20〜30%報告されています。
-
特に 若年層や筋肉量の多い男性、運動量の多い職種 で訴えが強く出る傾向があります。
4. 姿勢筋の萎縮による筋不均衡
-
頚椎の深層筋(多裂筋、棘筋など)が術後萎縮すると、僧帽筋や肩甲挙筋が代償的に働きやすくなり、慢性的な肩こり症状を悪化させるケースがあります。
②前方除圧固定術(ACDF)
ACDFとは、頚椎前方からアプローチして椎間板や骨棘などによる神経の圧迫を除去(除圧)し、固定材(ケージやプレート)を使って脊椎を安定化(固定)させる手術です。
東京脊椎クリニックでは手術用顕微鏡を用いてより精密に手術を行っています。
「頚椎椎間板ヘルニア」や「頚椎症性神経根症」「脊髄症」などの治療に用いられます。
⚙️ 術式の流れ(標準的な1椎間の場合)
-
頚部の皮膚を横切開(3〜5cm)
-
鎖骨上あたりを横に切開。声帯や気管、食道を避けて操作。
-
-
椎間板・骨棘の摘出
-
顕微鏡やルーペ下で、神経を圧迫している椎間板や骨棘を丁寧に除去。
-
-
ケージや自家骨の挿入
-
除去した椎間スペースに、人工ケージ(チタンやPEEK材)または腸骨から採取した自家骨を挿入。
-
-
チタンプレートなどで椎体を固定
-
前面にプレートをネジで留め、椎体を安定化。
-
-
皮膚縫合・閉創
-
ドレーンを留置して皮膚を縫合。術後数日でドレーン除去。
-
🔵メリット(長所)
1. 神経の除圧効果が高い
-
椎間板や骨棘による神経根・脊髄への圧迫を「前から直接」取り除くため、除圧効果が極めて高い。
2. 椎体の安定性が得られる
-
ケージやプレートで骨同士を固定するため、術後のぐらつきが少なく、再狭窄が起きにくい。
3. 頚椎アライメント(前弯)を再建できる
-
加齢や変性で崩れた頚椎の「自然な湾曲(前弯)」を人工ケージの高さで矯正できる。
4. 術後の疼痛コントロールが良好
-
術後の神経根痛やしびれが、術当日〜数日内に劇的に改善するケースも多数。
🔴デメリット(短所)
1. 可動域が制限される
-
椎間が「骨癒合」するため、その椎間の可動性は失われ、首の動きが全体的にやや硬くなる。
2. 隣接椎間への影響(Adjacent Segment Disease)
-
固定した部位の上下にある椎間板へ負担が集中し、数年後に変性や再発(新たなヘルニア)が起こることがある。
3. 嚥下障害・嗄声のリスク
-
前方アプローチのため、術後に**一時的な嚥下しづらさ、声のかすれ(反回神経麻痺)**が起きることがある(約5〜10%)。
-
多くは2週間〜数ヶ月で自然回復します。
-
4. 人工材料に伴う合併症
-
チタンやPEEKケージが**ずれる(移動)・沈み込む・癒合しない(偽関節)**などのトラブルもまれに報告される。
🩺 適応疾患
-
頚椎椎間板ヘルニア(C5/C6やC6/C7が多い)
-
頚椎症性神経根症(肩〜腕のしびれ・痛み)
-
頚椎症性脊髄症(歩行障害や巧緻運動障害)
-
脊椎不安定性(すべり症、偽関節)
-
外傷性椎間板損傷
頚の前側からアプローチし、椎間板や骨棘を取り除き、ケージやプレートで固定します。
- メリット:神経への圧迫が直接解除でき、自然な頚椎の湾曲が保てる
- デメリット:可動域が制限される、嚥下障害や声のかすれのリスク
③内視鏡下手術(PECDなど)
**PECD(経皮的内視鏡下頚椎椎間板摘出術)**は、直径7mm前後の細い内視鏡を用いて、頚椎の神経圧迫を最小限の侵襲で取り除く術式です。
2000年代以降、腰椎での応用が進んでいましたが、最近では頚椎領域にも導入され、特に単椎間の椎間板ヘルニアや神経根症において高い効果が報告されています。
🎯 主な適応疾患
PECDは以下のような疾患に適応されます:
-
頚椎椎間板ヘルニア(特に外側型・神経根圧迫型)
-
軽度の神経根症(肩〜腕のしびれ・放散痛)
-
後外側の骨棘形成による神経根圧迫
-
外傷後の軽度椎間板逸脱
※中枢型脊髄圧迫(脊髄症)や多椎間狭窄、後縦靱帯骨化症(OPLL)など、広範囲・高度な狭窄には不向きです。
⚙️ 術式の基本構造
① 体位と麻酔
-
全身麻酔にて行います
-
神経刺激機をつかいながら電気刺激に対する反応を確認しながら行います
② アプローチ方法
-
**前方アプローチ(transdiscal or transforaminal)**が主流。喉元近くから針を刺し、内視鏡と器具を挿入
-
頚部の筋肉や靭帯をほとんど切らずに進入
③ ヘルニア摘出と神経減圧
-
内視鏡下で突出した椎間板や骨棘を摘出
-
神経の圧迫をリアルタイムで視認しながら解除
④ 創閉鎖
-
傷口は約8mm程度。縫合不要なこともあり、美容的にも優れる
🔵メリット(利点)
1. 最小侵襲での治療が可能
-
皮膚・筋層・靭帯の切開がほぼないため、出血量はほとんどゼロ〜数cc
-
組織損傷が少ないため、術後疼痛が非常に軽度
2. 日帰り or 短期入院が可能
-
術後数時間の観察で帰宅可能なケースもあり、入院期間は1泊2日が標準
-
社会復帰が早く、デスクワークなら翌日復帰も可能
3. 構造温存による可動域維持
-
ケージやプレートを使用せず、骨癒合も行わないため、可動性を保ったまま神経症状だけを改善できる
4. 再手術にも対応しやすい
-
組織の温存により、万が一の再発や他の部位への手術時もアプローチが容易
🔴デメリット・限界
1. 術式適応が限定的
-
中央型ヘルニアや高度脊髄症、骨化病変(OPLL)には適さない
-
重度の椎間板変性、すべり症、不安定性には不向き
2. 技術的難易度が高い
-
内視鏡下での手術には高度な訓練・経験が必要
-
術者依存性が強く、未熟な手技では再発・神経損傷リスクもある
3. 完全除圧が困難な症例あり
-
脊髄症のように広範囲の減圧が必要な場合、十分な除圧ができない可能性
小さな皮膚切開から内視鏡で患部を処置する最新の低侵襲手術です。
- メリット:傷が小さく、回復が早い
- デメリット:対応できる病変が限られる
4. 術式選択のポイント
患者様ごとの症状、画像所見、年齢、職業などにより、術式の選択は慎重に行う必要があります。
- 1〜2椎間の椎間板ヘルニア → 頚椎前方固定術
- 多椎間にわたる脊柱管狭窄症 → 椎弓形成術
- 低侵襲を希望・単椎間狭窄 → 内視鏡手術
5. まとめ
頚椎手術は適切に行えば、日常生活の質(QOL)を大きく改善することができます。術式にはそれぞれ利点とリスクがあり、画像診断や神経所見、生活スタイルなど総合的に判断して選択することが大切です。
当院では頚椎疾患の専門医が、患者様一人ひとりに最適な治療法を提案し、最新の低侵襲手術にも対応しています。お気軽にご相談ください。
首の痛み・腰痛・手足のしびれ・他痛みでお悩みの方
東京脊椎クリニックまでお気軽にご相談ください
📞03-6807-7078
〒114-0013
東京都北区東田端2-11-11