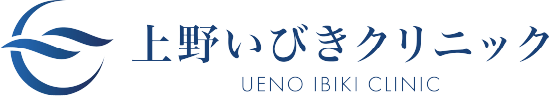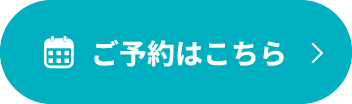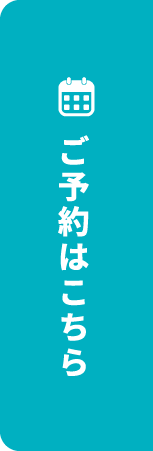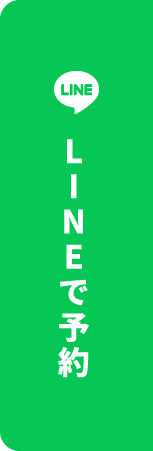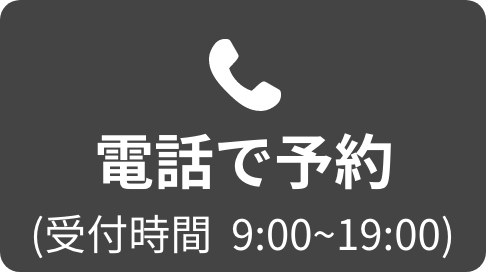いびきが引き起こす身体への影響

いびきは様々な身体に悪影響をもたらします。さらに心臓や神経の疾患へつながることも多く注意が必要です。
しかしその疾患自体がいびきから来ていると判断することが医師でも難しくその疾患自体の治療に注力していまい
根本原因を見逃しているパターンも多くあります。
今回はいびきによってもたらされる様々な身体への悪影響や疾患について解説します。
この記事の目次
睡眠の質低下による全身の疲弊
いびきの最大の問題は、その「音」そのものではなく、その発生メカニズムにより睡眠が分断されることにあります。
いびきをかいている最中、気道は狭まり、十分な空気が肺に届きにくい状態となっています。
この状態が繰り返されることで、体は断続的に覚醒反応を起こし、結果として深い睡眠(ノンレム睡眠)に到達する時間が極端に少なくなります。
ノンレム睡眠は、身体の修復・免疫の再構築・ホルモンの分泌といった回復プロセスに不可欠な時間帯です。
この深い睡眠が妨げられることで、翌日の疲労感、倦怠感、集中力の欠如など、日常生活に支障をきたす症状が慢性化していきます。
加えて、成長ホルモンの分泌量も減少するため、肌の代謝低下、筋肉の修復能力の鈍化、さらには糖代謝異常の原因にもなりうるのです。
さらに深いノンレム睡が不足し、身体の回復力や免疫力が低下します。
また、血中の酸素濃度が繰り返し低下することにより、心臓や脳に負荷がかかり、動脈硬化を進行させる要因ともなります
慢性的な交感神経の緊張状態
いびきにより気道が断続的に狭窄されると、体はそれを“呼吸危機”と捉えて、交感神経が優位になります。
交感神経とは、心拍数や血圧を高め、身体を「戦闘モード」にする自律神経系の一つです。
睡眠中は本来、副交感神経が優位となって心身が休息に向かうはずですが、いびきによる気道抵抗や覚醒反応があると、その切り替えが起きず、夜通し“軽い戦闘状態”が続くことになります。
これにより、心拍数の持続的上昇、血圧の夜間非低下(dippingパターンの崩壊)、睡眠中の交感神経興奮による夜間頻尿や寝汗、翌朝の強い頭痛や動悸といった症状が見られるようになります。
特に、夜間血圧が下がらない状態(non-dipper型高血圧)は、心血管リスクが高まるとされており、いびきを侮るべきではありません。
酸素供給の不安定化と循環器系への負担
いびきをかく際、気道が振動しているということは、その空気の流れがスムーズでないことを意味します。
つまり、肺に送り込まれる酸素の量が一時的に減少し、体内の酸素飽和度が断続的に低下している状態です。
いびきは、狭くなった上気道を空気が通過する際に粘膜や周囲組織が振動して生じます。
流れが乱れている=換気が効率的でないことを意味し、その間は肺に送り込まれる酸素が相対的に不足します。
結果として血中の酸素飽和度(SpO₂)が断続的に低下し、睡眠中に小さな低酸素エピソードが繰り返されます。
この断続的低酸素は全身に連鎖的な影響を及ぼします。
まず、血管の内皮細胞がストレスを受け、血管の拡張・収縮のバランスが崩れて弾力性が低下し、動脈硬化の進行を後押しします。心臓にとっては、酸素需要が高い状態にもかかわらず供給が揺らぐため、拍動数や交感神経活動が高まり、長期的には左心肥大や心不全のリスク上昇につながります。
さらに脳では、特に高齢者で夜間の軽度虚血が積み重なることで、注意力や記憶などの認知機能に微細な悪影響を及ぼす
可能性が指摘されています。
つまり、いびきは単なる音の問題ではなく、睡眠中の低酸素が全身の血管・心臓・脳に負荷をかける生体シグナルであり、放置せずに評価と対策を検討すべき状態といえます。
代謝異常と肥満の悪循環
質の悪い睡眠は、食欲をコントロールするホルモンバランスを乱します。
レプチン(満腹ホルモン)の分泌が減少し、グレリン(食欲増進ホルモン)が増加するため、いびきをかいて睡眠が分断された人は、日中に過食傾向になりやすくなります。
結果として体重が増加し、首まわりや舌根部に脂肪が沈着し、さらに気道が狭くなっていびきが悪化するという「負のスパイラル」が形成されてしまうのです。
また、インスリン抵抗性の上昇や脂質異常症との関連も指摘されており、いびきが生活習慣病の温床になりうることが明らかになってきました。
精神面への影響と日中パフォーマンスの低下
いびきをかいている人の多くが、朝の倦怠感やぼんやりした感覚を訴えます。
これは深い睡眠がとれていない証拠であり、脳が十分に休息できていないことを意味します。日中の眠気、仕事の集中力や判断力の低下、感情のコントロール不全(イライラ・落ち込み)これらの症状は、生活の質(QOL)の低下のみならず、仕事や人間関係、家庭生活にも悪影響を及ぼします。
また、慢性的な睡眠不足は、うつ病や不安障害の発症リスクを高めることが臨床的にも知られており、「いびきが続く=精神衛生の悪化」という構図は、見逃せない重要な視点です
医療現場からの視点

私は20年以上にわたり麻酔科医として手術に携わり、年間500件以上の症例を担当してきました。
麻酔科医は手術中、患者さんの頭側に位置し、呼吸や循環、神経反応など全身状態を継続的にモニタリングします。
全身麻酔では気管内挿管といって患者さんの気道に気管チューブを挿入し、呼吸と筋弛緩薬で止め手術中は人工呼吸となります。そのためいびきをかくことはありません。
しかし近年では静脈麻酔を使った低侵襲手術が増えており、患者は自然呼吸のまま眠ります。
このとき、驚くほど多くの人がいびきをかいていることに私は気づきました。
しかも、自覚がない人がほとんどです。
そして大きないびきをかく方においてかなりの割合で前述した、睡眠時無呼吸を起こしており、そんも患者さんの背景を調べてみると、肥満や高血圧、糖尿病などを併発していることがわかりました。
これまでに1万人以上の眠りを見守ってきた私の実感として、いびきは極めて一般的な現象でありながら、軽視すべきでない症状であると断言できます。
いびきは身体からの警告信号
「ただのいびき」と思っていたら、実は重篤な疾患の入り口だった──そんなことは決して珍しくありません。
いびきは、身体が何か異常を訴えているサインであり、生活習慣や身体の構造、疾患の影響が複雑に絡み合っています。
今回は、いびきがもたらす健康被害として睡眠時無呼吸症候群の分類、原因、そして関連疾患について解説しました。