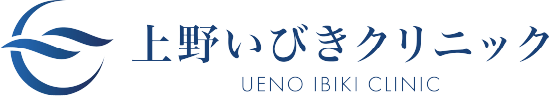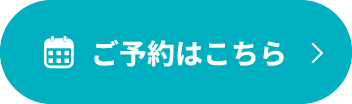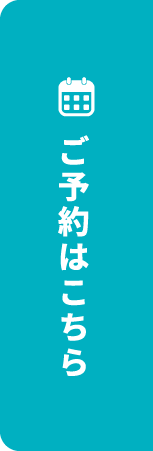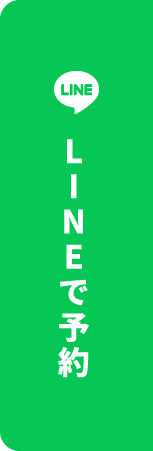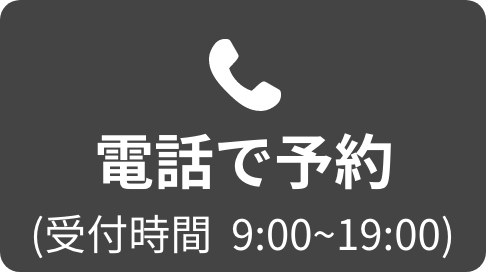睡眠時無呼吸症候のタイプ別分類とは

睡眠時無呼吸症候群は、呼吸が止まる「原因の違い」によって 3つのタイプ に分けられます。
それぞれ原因も治療方法も少しずつ違うので、正しく分類することが大切です。
この記事の目次
閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)
最も多いタイプで9割以上を占めるます。
睡眠中に空気の通り道である「上気道」、特に咽頭部(のどの奥)が物理的に閉じてしまうことで、何度も呼吸が止まってしまう状態です。これは非常に多くの睡眠時無呼吸のケースに見られるものであり、全体の9割以上がこの閉塞型に分類されるとされています。
特徴的なのは、「本人は呼吸しようとしているのに、空気が通らない」という点です。胸やお腹の動き、つまり呼吸の運動そのものは続いているにもかかわらず、気道が塞がれているために酸素が取り込めない。
その結果、血中の酸素濃度が低下し、脳が窒息状態を感知して「呼吸を再開しろ」と強制的に覚醒させます。
この“目が覚める”という現象は、本人にとって自覚がない場合も多く、実際には数秒から十数秒間の無呼吸が一晩に何十回、時には百回以上も繰り返されています。知らぬ間に「眠っているはずが休めていない」状態が続いていくのです。
のどの奥(咽頭)が ふさがってしまうことで息が止まるという状態になっています。
この現象を、わかりやすく説明するために、ストローを使った例えがあります。
たとえば、指でつぶしたストローでジュースを吸おうとすると、いくら頑張っても空気や液体が入ってこないのと
同じように、OSAでは気道という名の“ストロー”が物理的に潰されてしまうのです。
さらに悪いことに、この状態が何度も繰り返されると、睡眠のリズムは分断され、体は夜通し“窒息→覚醒→呼吸再開→再び無呼吸”のサイクルを延々と繰り返すことになります。
まさに、**見えないところで行われる「静かな戦い」**なのです。
中枢性睡眠時無呼吸(CSA)
呼吸中枢の異常により呼吸が止まる状態で、心不全や脳卒中の既往歴がある人に多く、のどはふさがっていないのに、脳から「息をしろ」という指令が出ないために呼吸が止まるのが特徴です。
具体的には、呼吸運動を指示する延髄や脳幹部の神経活動が一時的に停止し、胸や横隔膜を動かす命令が送られなくなるのです。
つまり、喉がふさがって空気が通らないOSAとは異なり、CSAでは気道に物理的な閉塞はないにもかかわらず、呼吸そのものが止まるという、より中枢的な障害による無呼吸です。
CSAの原因は複数ありますが、大きく分けて以下のようなものが知られています。
1. 心不全などの循環器疾患
心臓のポンプ機能が低下している心不全患者では、血液の流れと呼吸中枢との連携にズレが生じ、
呼吸のタイミングを調節する機能が不安定になることでCSAを引き起こします。
このタイプのCSAは「Cheyne-Stokes(チェーン・ストークス)呼吸」と呼ばれる、呼吸が浅くなったり深くなったり
を繰り返すパターンを示すことが多く、夜間の心不全悪化の兆候ともなります。
2. 脳卒中・脳血管障害
脳幹や延髄の損傷があると、呼吸をコントロールする神経そのものが機能しなくなり、CSAが出現することがあります。
3. 薬物の影響
特にオピオイド系鎮痛薬(モルヒネやフェンタニルなど)の長期使用は、呼吸中枢を抑制し、
CSAを引き起こすことが知られています。
4. 高地での睡眠
高山地帯など酸素が薄い環境では、呼吸中枢が過剰に刺激されたり抑制されたりして、
周期性呼吸の変動=中枢性無呼吸が発生することがあります。
これは「高地性CSA」と呼ばれ、比較的一過性のことが多いです。
これは、夜間に体が「息をしようとすることすら忘れてしまう」ような状態といっても過言ではありません。
呼吸筋は働いておらず、空気の出入りが全くないため、周囲の人にもいびきが聞こえない静かな無呼吸であることが多く、非常に気づかれにくい傾向があります。
混合性睡眠時無呼吸
OSAとCSAの両方が混在するタイプ。
混合性無呼吸の特徴は、静かな無呼吸から始まり、次第に体が呼吸を取り戻そうとして必死に努力し始めるという点にあります。
患者さんの睡眠中の様子を観察すると、はじめは完全に無音(いびきすらない)状態から、徐々に呼吸音が再開しますが、それにともなっていびきが強くなったり、体が身じろぎするような動きを見せたりします。
この「無音→努力→いびき再開」の流れが、混合型の典型的なパターンです。
混合性無呼吸の診断は、**一晩にわたる精密な睡眠検査(PSG:睡眠ポリグラフ)**によって初めて可能となります。
呼吸の努力(胸部・腹部の動き)をセンサーで捉えることで、「呼吸努力があるかどうか(=閉塞性か中枢性か)」を見極めます。
とくに、CPAP開始後に患者が“眠れない”“違和感がある”と訴えるケースでは、混合型を強く疑う必要があります。
なぜなら、OSAのつもりで治療を進めていたにもかかわらず、CSAが現れてしまうことで、治療が逆効果になっている可能性があるためです。
このように混合性睡眠時無呼吸タイプは非常に診断が困難な場合があります。
混合型への対応
呼吸補助療法の再選定が鍵
混合性睡眠時無呼吸に対しては、単純なCPAPでは対応が難しいことがあります。
特に、中枢性成分が強い場合には、以下のような**「高度な呼吸補助療法」**が検討されます。

ASV(適応型サーボ換気:Adaptive Servo-Ventilation)
ASVは、患者の呼吸パターンをリアルタイムに解析し、必要に応じて圧力や換気量を自動で調整する最新の換気装置です。
中枢型睡眠時無呼吸(CSA)と閉塞型睡眠時無呼吸(OSA)の両方に対応できるのが大きな特徴です。
ただし、心不全を合併している患者では禁忌となる場合があるため、導入の際は心機能を含めた慎重な評価が必要です。
二相性NIPPV(非侵襲的陽圧換気:Bilevel NIPPV)
二相性NIPPVは、吸気時と呼気時に異なる圧力をかける方式で、呼吸をサポートします。
閉塞型の要素が強い混合型睡眠時無呼吸において、吸気を助けながら呼気時の負担を軽減できる点が特徴です。
OSA優位の混合型患者に効果が期待できます。
混合型の治療が難しい理由と長期的対応
混合型睡眠時無呼吸は、
-
見逃されやすい
-
他のタイプと誤診されやすい
-
通常の治療法が合わない
という3つの難しさがあります。
そのため、睡眠医療に精通した専門医による診断と継続的なモニタリングが不可欠です。
また、装置の使い心地(忍容性)や生活の質(QOL)を保つことも重要です。
患者ごとに、装置の種類・圧設定・マスク形状などを丁寧に調整しながら、長期的に最適化していく必要があります。